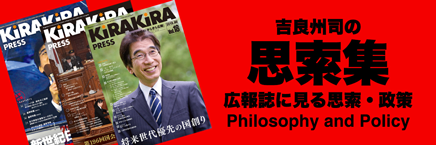22年前に執筆した「デフレに思う」 その1
予告通り、22年前の「吉良州司と元気な大分」のホームページに掲載した「デフレに思う」の前半部分(その1)を掲載します。
デフレに思う
今、デフレ対策、デフレ退治という言葉が毎日のように新聞を賑わせていますが、日本経済新聞の特集記事の中に、「デフレの進行を多角的な視点から捉え、その原因を不良債権問題だけに求めず、より広い視野、即ちグローバリゼーションや技術革新などの視点から捉える必要性を『インフレの世紀がむしろ例外』だという点も披露しながら強調している」記事がありました。戦後、長いこと慣れてしまっていたインフレがむしろ例外で、歴史的にはデフレが主流だという内容には驚かされました。
「デフレ」というと「全てが悪」のように聞こえますが、諸物価が下がるという一面だけを捉えると、年金で生活する高齢者や賃金が毎年上昇しなくなった企業に勤める人々、一般の消費者にとってはむしろ歓迎すべきことです。
私は「デフレの進行が、日本が戦後システムという制度疲労に陥った古い社会・経済体質や価値観から脱却し、全く新しい政治、経済、社会システム、伝統を重んじつつ新時代に対応する新しい価値観をもたらす契機になリうる」いや「災い転じて福となる」ようにしなければならないと思っています。
勿論、短期的視点では国民全体が大きな痛みを伴う「産みの苦しみ」に耐える覚悟が必要でしょう。しかし、長期的視点に立った時、必ずやかけがえのない子孫の為になるという強い信念で、この厳しい状況を乗り切らなければならないと思っています。
我々は、あの敗戦直後の廃墟の中から、驚異的な復興を成し遂げた世代の孫子です。やってやれないことはない、乗り切れないことはない と信じています。
1.グローバリゼーション、技術革新の影響
「人も生き物」「経済も生き物」である以上、現実に生きている人や企業の偽らざる欲求(デフレ退治とインフレ期待)を政治家や経済界のリーダーが無視するわけにはいかないことは十分承知しています。
しかし、バブル期に獲得した経済的権益と期待利益水準は(例えば、個人の給与水準や企業の売上・利益計画・目標)、その崩壊により、実力以上のものであったことが判明してしまった以上、それを実力相応に戻すことがまず先決、次にはバブル以前の「実力相応の水準」に戻しても、その実力で国際競争に勝てる水準なのかの検証が必要だと思っています。
ベルリンの壁崩壊の1989年、ソ連崩壊の1991年以前には東西の壁が厳然として存在し、現在のように中国が世界の工場として台頭しておりませんでしたので、バブル以前の日本経済は「まだ西側完結経済」の中での繁栄と言えただろうと思います(勿論、ソ連崩壊以前、ベルリンの壁崩壊以前にも東側経済を利用していたことは事実ですが)。
ところが今や、旧東側諸国、特に中国のメガコンペティション参入により、東西間を隔てていた経済格差、賃金格差、物価格差のダムが決壊し、西側の賃金水準や物価水準の水位が怒涛の如く、東側に流れ込んでいますので、この水位が同じになるまで、今後も賃金、物価の下落圧力が加わり続けるだろうと思います。
また、技術革新、特にIT技術の飛躍的な進歩がその傾向に拍車をかけていることも間違いありません。
2.今あるもので十分。ものを大事に使おう という消費者心理
更に、日本だけでなく、先進国ではIT関連、環境関連、健康関連、知的好奇心関連商品・サービスを除いて「今すぐどうしてもほしいもの」がほとんどなくなってきています。
今持っているものを「大事に使えばまだまだ使える」という風に技術革新(最新技術の商品が安く長く使える)の恩恵をうけています。
上述した関連商品、サービスや、携帯電話、パーソナル・コンピューター、プラズマテレビなど、まだまだ技術革新に基づく新製品の新規需要は伸びるとは思いますが、驚異的な技術進歩の速さと東西経済融合によって「いいものがすぐに安くなる」ことを肌で知っている一般の人々は現時点では高価な商品に今すぐ大挙して押し寄せるようなことはしません。2-3年後には半値、八掛け以下になることが分かっていますから、それからでも遅くないと思っているでしょう。
3.総人口、生産年齢人口の減少
15歳~65歳の生産年齢人口は既に減少に転じており、2006年には総人口も減少に転じます。当然のことながら、一人一人の消費支出額が増えない限り、需要が増えるわけはありません。
このような中で、国内でもメーカー数が多いのに加え、中国が世界の工場となる過程で、安くて高品質の製品が出回り、供給過剰がおきています。そんな中で、毎年毎年、売上、利益増加を期待するのはトヨタ、キャノン、ソニーなど元々技術水準、生産性水準が高く、トップの強いリーダーシップが発揮されてきたほんの一部の企業、業界を除いて無理があります。勿論、リエンジニアリングにより増収・増益、100歩譲って減収・増益体質を追及することは必要ですし、それが経営者の腕に見せ所でもあり、実現も可能でしょう。しかし、少なくとも、ほとんどの企業の売上が毎年伸びるという状況にはないと思います。
4.1990年代は世界的なファイナンス時代、将来需要先食い時代
私は、国際版のPFI(プライベート・ファイナンス・イニシアティヴ)手法であるインフラストラクチャー(社会基盤整備)のBOT/BOO(民間活力利用型)プロジェクトに従事しておりました。それゆえ、仕事を通して実感していたのですが、1990年代は、「小さな政府」志向の影響で、アジア、中南米、東欧諸国の政府資産、公社・公団が「民営化」という名目で売りに出されていました。また、民間活力利用、民営化の先端手法であるであるPFI/BOT/BOO手法がなければ、遠い先の将来にしか実行できなかったであろうインフラストラクチャー部門への投資が「分不相応」「実力以上」であるにも拘らず、90年代前半、半ばに集中投資されたことも事実です。
この時期のファイナンス手法による将来需要の先食いも現在や近い将来の需要不足の一因だと思っています。アジア危機の原因の一端もここにあったでしょうし、アルゼンチンの経済、財政破綻もこの要素が強いと理解しています。
吉良州司