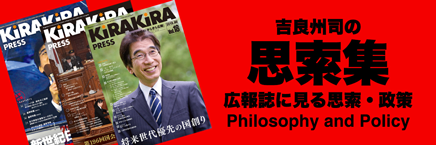ロシアによるウクライナ侵攻前からの吉良州司の切なる訴え 議事録含む
ウクライナ戦争の早期停戦を目指して米国トランプ大統領が活発に動いており、インフラ関連施設への攻撃を禁止するといった、枝葉(えだは)のことは合意できそうですが、一番肝心のロシアが占領している東部南部4州およびクリミアの主権問題、帰属問題については(報道によると)触れられていないようです。ウクライナのNATO加盟問題は米国が否定的であることも報道されています。
この占領地域の帰属問題とNATO加盟問題に対する合意こそが停戦の必須条件なのですが、現時点では、米露間、米ウ間の交渉では前進していないようです。
前回のメルマガでは、これらの問題にも明確な条件を提示した、下記のような「現状に照らした停戦条件」(要約版)について吉良州司の考えをお伝えしました。
1)ウクライナの中立化(NATOへの非加盟)、しかし、非武装化には応じない
2)クリミアとドネツク人民共和国、ルハンシク人民共和国のロシアへの割譲
3)東部南部4州中、ロシア占領地域は、ロシア主権は認めないが、ロシアの実効支配を現時点では黙認し、主権の帰属は将来決める。
4)ロシアとクリミアおよび黒海沿岸の国際港を陸路で繋ぐ回廊を設ける
5)人質全員の送還(両国の人質数に差があっても、全員を送還)
6)ウクライナ大統領選挙の実施またはゼレンスキー大統領の辞任
7)国連安全保障常任理事国、または、フランス、ドイツ、トルコによるウクライナの安全保障
8)ロシア主権を容認した以外の地域からのロシア軍の即時撤退
9)対ロシア経済制裁の段階的解除
上記の停戦条件案を含め、吉良州司の主張はロシアに甘すぎるという反論が多数寄せられてきました。しかし、私はロシアの立場に立てばロシアの論理、ロシアの正義があると主張し続けてきました。核を保有し、且つ脅しにも使う獰猛なロシアが相手です。しかも、元KGB諜報部員として、スパイ映画に出てくるような、何をするかわからない、否、どんなことも平然とやり抜くプーチン大統領が相手です。そのロシアにウクライナを侵略する口実を与えてはならなかったのです。
米国も他の欧州諸国も判断を誤りました。何よりもゼレンスキー大統領にその配慮が欠けていました。
ウクライナのNATO非加盟を宣言すれば、ロシアによる侵略を未然に防ぐことができたのです。それを米国も、欧州NATO加盟諸国もウクライナの現政権もロシアの真意を読みきれず、間違った判断と行動をしてしまいました。今、ロシア優勢下において停戦に持ち込むためには、クリミア、ドネツク人民共和国、ルハンスク人民共和国の割譲を含むロシアの言い分にも応えていく必要があると思います。それ故、上記の停戦条件案を提示しているのです。
私が、ロシアがウクライナに戦争をしかけると確信を持ったのは、ロシア侵攻の約1か月前の2022年1月26日に当時の米国ブリンケン国務長官が「ウクライナ情勢をめぐってロシア側が出していた要求(NATOをこれ以上東方拡大させないこと)に文書でゼロ回答した、とのBBCニュースを聴いた時でした。
このままでは、「演習」と称してベラルーシに終結させていたロシア軍がウクライナに攻め込んでしまう。そうなれば、何の罪もないウクライナの人々が犠牲になってしまう。また、侵攻の結果、天然ガスをはじめとする化石燃料や小麦などの穀物価格が高騰して世界中を苦しめてしまう、と危機感を募らせました。
中でも最も大きな痛手を被るのは資源と小麦など食料を輸入に頼る日本であるとの危機意識を強く持ちました。
それゆえ、最初は2022年の2月8日の予算委員会、続いて2月16日の予算委員会外交分科会において、「ウクライナのNATO加盟を思いとどまらせてほしい。ウクライナ有事により、同じく大きな打撃を被るであろうドイツと連携して、ロシアによるウクライナ侵攻を阻止するよう、日本政府、外交当局に行動してほしいと訴えたのです。
以下は、ロシアによるウクライナ侵攻前の2月16日の予算委員会外交分科会の議事録(編集なし)です。上記の危機意識に加え、侵攻によりロシアと中国が接近することのリスクなどにも言及する吉良州司の切なる訴えを一読して戴けるとありがたく存じます。
吉良州司
<2022年2月16日予算委員会第3分科会(外交) 有志の会吉良州司質問議事録>
この質疑の動画はこちらから見ることができます
○ 葉梨主査 これにて渡辺周君の質疑は終了いたしました。次に、吉良州司君。
○吉良分科員 有志の会の吉良州司でございます。
林大臣、まずはメルボルンでのクアッド、外相会合、そしてハワイでの日米韓外相会合、お疲れさまでした。
私自身は、総理大臣だとか外務大臣を国会に張りつけておくということについては物すごい問題意識を持っていますので、本当はこういう形で時間をいただくのも気が引けるんですけれども、有志の会になって、質問時間が八分だったり十二分だったりということもあって、この三十分という時間をもらえたということでちょっと飛びつかせてもらいました。その辺は御容赦いただきたいと思います。
そうはいっても、実は、質問通告をさせてもらいまして、昨日、事務方の皆さんと質問レクをさせてもらった際に、私が掲げた質問というのはほぼ全部アウト。アウトという意味は、とても正面から答えられない質問ばかりを並べていたということで、いろいろと事務方の人とも話し合った中で、政府として答えられないかもしれないけれども、私の方の問題意識として、議事録にも残し、そして外務省の皆さんにもきちっと聞いていただく、そういう思いで、多少、多少というよりもかなりの部分、私の独り語りの時間になるかもしれませんけれども、その辺は御容赦いただきたいと思っています。
まず最初に、実は先日、二月三日の予算委員会において、北方領土というテーマを取り上げたんですけれども、実は、北方領土といいながら、前半の、貴重な八分の四分ぐらいを使って、ウクライナ問題の問題意識を披露させていただきました。
ちょっと念のためにもう一回、その議事録が今ありますので読ませていただきますと、北方領土問題を取り上げようとしたきっかけは、実は、ウクライナ問題、ウクライナ決議案です。これを契機に、あれこれ考えました。
ロシアの真意は一体どこにあるのか。クリミアや東ウクライナは、歴史的に見れば、語弊があるかもしれないけれども、ロシアの領土であってもおかしくないのではないか。けれども、当時は、ソ連内共和国、国内共和国であったがゆえに、つまり、将来的にその国内共和国が独立しようなどとは想定していなかったがために、ソ連崩壊後、いろいろな問題が出てきている。議事録じゃなくて、私、補足させてもらうと、もし将来独立することがあり得るというソ連内共和国であったならば、私は、今の東ウクライナとクリミアの位置づけは元々違っていたんだろうという問題意識を持っています。もう一回議事録に戻りますと、さらには、NATOは、元々、ソ連とワルシャワ条約機構の軍事的脅威に対して、欧州の平和と安全を守るためにつくられた同盟であるにもかかわらず、今次、ウクライナ問題では、ロシアとの、場合によっては軍事衝突もあり得るかもしれない。にもかかわらず、更に東方拡大を目指すゆえんは一体何なのか。それから、ウクライナ問題がロシアの東アジア戦略にどう影響を及ぼしてくるのか。結果的に我が国にどう影響を及ぼしてくるのか。さらには、中国が、このウクライナ問題を契機として、どのような国益を追求してくるのか。
さらには、中国は、もしかしたら、米国が中間選挙を前に、対中国、対ロシア、二正面作戦を実行する余裕はとてもない、そういう足下を見て、一挙に台湾を狙ってくるのではないか。ただ、待てよ、よく考えたら、今年、中国共産党大会もあり、習近平氏も三期目を狙う。とてもじゃないけれども、また、準備も整っていないので、それはないだろうか。
あれやこれや、商社マン時代の習性で、風が吹けばおけ屋じゃないですけれども、誰がもうかるのかと、あれこれ考えた次第です。もうちょっと聞いてください。
我が国としては、中国とどう向き合っていくかというのが外交上最大の課題だ、そういう認識を持っていますが、その中で、ウクライナ問題の対応いかんによって、ロシアと決定的な関係悪化を招いてはいけない、また、これを契機にする、中ロの更なる接近についても備えなければいけない、このような思いから、北方領土を取り上げましたというふうに問題提起をさせていただきました。
これに対して、実は、林大臣の答弁の冒頭、こういう発言がありました。
先生、私の元商社マンらしい思い巡らせを、私も元商社マンとして今お聞かせいただいたところでございますと。それから答弁をいただいたんですね。
実は、先ほど読みました、時間が何と八分しかなかったので、はしょった質問があったんですね。どういう質問かといいますと、林大臣も元商社マンなので、外交交渉はもちろん、国際ビジネスの交渉において一〇〇対ゼロなんてあり得ないですよねと。交渉においては、譲らないものは絶対に断固として譲らないという覚悟を持って、けれども、かち取るべきものをかち取るために何かを譲るという腹は決めて、そこで、ある事項を譲りながら、かち取るべきものは必ずかち取る、これが外交交渉でもあり、私たちが経験した国際ビジネス交渉でもあり、一〇〇対ゼロというのはないというふうに思っています。これは質問通告はしていないんですけれども、前回聞こうと思った幻の質問として、大臣に、一〇〇対ゼロはないということを、御自身の御経験も踏まえて、また、今はもう外交の最前線に立っておられますので、そのことについて大臣の見解をいただければと思います。
○林国務大臣 大変奥の深い御質問をいただきまして、ありがとうございます。
委員におかれましては、日商岩井時代にニューヨークに御勤務して、世界中の情報が集まってくるところで最前線におられた。私の場合は、たばこの原料を扱っておりましたので、比較的そういう農産物の、田舎と言うと恐縮ですが、中南米ですとかトルコ、ブルガリアあたり、行ったり来たりしておりましたが。
そういう意味で、今お話を聞いておりまして、まず、一〇〇対ゼロの話の前に、過去どうであったか、そのことも、私、実は、この間、非常に感銘を受けたわけでございますが、ロシアがかつてソ連であったときの思いというものを引かれながらこのお話をされたということで、やはり、我々、交渉を商社のときにしておりましたときも、今でもそうでなくてはならないと思いますが、自分が相手の立場であれば一体どういうことを考えて、本音で言うとどの辺りが譲れないものなのかということ、相手であったらどう考えるのか、これを知っておくことというのは大変大事な視点だろうということ。
もう一つは、釈迦に説法ですが、昔の言葉で、愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶということですから、相手の立場を考えるときに、歴史的にどうであったかということを知っておくということはとても大事なことだ、こういうふうに思わせていただいたところでございまして、そして、そうした観点からすると、私の方が一〇〇で相手がゼロということは、相手の立場に立って考えますと、それはあり得ないだろうということに当然なるわけでございますので、そういう立場も考えながら、その上で、商社の時代と違うとすれば、なかなか金額で幾らというふうに決められないものがあるんだろうと。お互い譲れない国益というものもあって、それを懸けて交渉するというところは少し違うところもあるのかな、そういうふうに考えております。
○吉良分科員 ありがとうございます。非常に得心のいく答弁、見解をいただきました。
癖として、常に、自分が相手だったらと、これはもう癖になっていて、本当に、相手だったらこう出てくるから、こっちはこう出てやろう、これが癖になっていますので、私なんか、外交上も今最前線に立ってはいませんけれども、そういう思いであれこれ考えるところでございます。
そういう中で、私が一点指摘したいのは、多くの国会議員も、そして実は、多くの国民も、事相手が中国だ、ロシアだとなると、これは価値観というか、価値の違う、価値観外交でいえば、違った価値観を持っているとか、それからまた、強権又は独裁国家だとなると、そういう強権国家が主張する外交的主張、要望というのは全て悪だ、だから、こんなもの一歩も譲るな、一〇〇対ゼロでいいから、一〇〇主張し続けて全部取れ、こういう強硬論が横行するということに対して、私は、非常に大きな実は危機感を持っています。強権国家であっても、冷静に考えたときに、その主張には、こちらがそれを受け入れるかどうかは別として、今大臣がまさにおっしゃったように、相手の立場に立ったときに、それはあり得るなという聞く耳が私は必要だというふうに思っているんです。
一方、私自身も、日本外交のまさにコーナーストーンである日米同盟、日米関係、これはもう最重要だとは思っていますけれども、私の問題意識としては、トランプ大統領を誕生させてしまったアメリカ、そしてアメリカ・ファーストを掲げて以降のアメリカ、これは、正直言って、一〇〇%信用していいのか。日本が自分たちの国益を守っていくために、常にアメリカについていく、これは危険であるとすら思っています。特に、イランの核合意からの離脱も含めて、明らかに国内向けのパフォーマンスで外交を展開している、そして、この中間選挙が終わるまでは民主党政権もトランプの幻影と戦い続けなければいけない、こういう状況にあるアメリカというものと完全に歩調を合わせていいのか、その結果、日本の国益を損なうようなことがあってはいけない、このような問題意識を持っています。ですから、そういう問題意識を持った上で、非常に漠としていますが、本来、ざあっと質問をしたかったものを独り語りするという中で、一つ。今、林大臣が、また日本の外交としてこのウクライナ情勢をどう見ておられるのか、その見解について簡潔にお聞きしたいと思います。
○林国務大臣 ウクライナ情勢の現状認識ということでございます。
バイデン大統領とプーチン大統領が、外交的な取組を継続する用意があるという旨を共に表明をされておられます。ロシア国防省はウクライナ国境周辺地域の部隊の一部撤収を発表する、こういう動きもあるわけでございますが、その一方で、バイデン大統領は、引き続き、ロシア軍によるウクライナ侵攻の可能性、これは明確に残っている、こうも述べられているわけでございます。我々としては、やはり、引き続き予断を許さない状況、これが続いているというふうに認識をしておりまして、高い警戒感を有して、懸念を持って注視をしておるところでございます。
当然、我々として、日本としては、ウクライナの主権、そして領土の一体性、これを一貫して支持してきておりまして、昨日の十五日でございますが、岸田総理が、ゼレンスキー・ウクライナ大統領との間で首脳電話会談を行われまして、こうした日本側の立場をお伝えしたところでございます。引き続き、G7を始めとする国際社会と連携して、適切に対応してまいりたいと思っております。
○吉良分科員 ありがとうございます。
今答弁いただいたことについては、反論しようがないというか、納得するところでありますけれども、私が先ほど言った、相手の言い分にも一理あるということについて、少し歴史的に振り返ってみたいと思うんですけれども。
歴史の専門家ではありませんが、ロシアは、古くはモンゴル、キプチャクハン国の支配を受け続けていた時期がある。タタールのくびきという言葉が残っているように、そのときの支配を受けたことについてのトラウマは残っていると思っています。
さらに、これは多くの方が意識していないんですけれども、第二次世界大戦で一番多くの犠牲を出した国はどこか。これは実は、私は驚いたんですけれども、国会議員の中で安全保障に詳しいと言われている方に聞いたときに、日本でしょうという答えが返ってきて、私はもう本当に椅子から転げ落ちそうになりました。
これはもう、ここにいらっしゃる方は全員御承知のとおり、独ソ戦で、当時のソ連、少なくとも二千万人以上、その後どんどん数字が膨れ上がっていますけれども、一応共有されているのは二千万人と言われています。ウクライナでいえば、当時のソ連ですから、今のロシアもウクライナもベラルーシも含んだ地域で二千万ですので、今のロシアだけというわけではありませんけれども、ロシアからしてみると、独ソ不可侵条約を破って攻め込まれてきて、二千万の命が、軍民の命が失われた、これは大きなトラウマだろうと思っているんです。
それがゆえに、東欧諸国、ワルシャワ条約機構で、ある種、緩衝地帯としたように、ロシアからしてみると、さっき言ったモンゴルの支配、それから独ソ戦、それを考えたときに、やはり緩衝地帯がないと不安で不安でしようがない。逆に、窮鼠猫をはむじゃないけれども、国境が接してしまうと、敵対関係にある、その方がリスクが高くなる。
ちょうど東アジアにおいては、中国が何であれだけ乱暴を働く北朝鮮に肩入れするのか。それは、米韓同盟がある中で、米国と事実上国境を接したくないから緩衝地帯として北朝鮮を生かしているわけで、それを考えたときに、ロシアのやはり緩衝地帯が必要だということについては、ある程度の僕は理解が必要だと思っています。先ほどおっしゃったウクライナ領土、主権の一体性を守る、これは重要なことだと思っています。けれども、かといって、武力紛争が起こり、結果的にウクライナの人たちが犠牲になる、そして、その軍事紛争の影響が、ヨーロッパのみならず世界的な経済的混乱を招く、経済で苦しむ人たちが出てくる。そこまでして、ロシアからしてみると、緩衝地帯にしてほしいという思いで、今、ある意味では演習という名の下に威嚇をしているんだと思いますけれども、私がロシアの立場だったら、そこは一理あると私は思っているんです。繰り返しますけれども、ロシアの肩を持つとかそういうことではない。最終的には日本の国益を守らなければいけない。だけれども、同時に、ウクライナ、そこで軍事紛争が起こったときに、傷つくのは、命を落とすのはウクライナの人です。私は、アフガニスタンにしてもイラクにしても、ここ最近起こっている戦争というのは、ある意味、米国が正義を掲げて戦争をしかけ、そしてその国において多大な犠牲が出て、そして、イラクでいえば、フセイン政権を崩壊させ、バース党を駆逐したことによって、バース党がISに入っていき、ISがあの中東地域に多大な混乱をもたらし、犠牲を強い、多くのイラク人、それからシリア人を犠牲にし、かつ難民に追いやっている。
このことを考えたときには、私は、絶対に軍事紛争を起こさない、そのためには、今言った、相手の立場に立って一理ある、そこを踏まえた対応が必要である、このように思っていますけれども、大臣の見解はいかがでしょうか。
○林国務大臣 ほかの国の状況や過去の状況等、比較対照にお使いになられながら、今の情勢の、客観的な情勢に加えて、相手がどういう意図といいますかポジションを持っているのかということを分析するということで、大変傾聴に値する御見解を披露いただいたというふうに思っております。我々、一般論になって恐縮でございますが、外交を行うときにはそういうことも頭の中に入れながらやっていくということでございますし、古典で孫子の兵法というのがございましたけれども、
己を知り相手を知れば百戦危うからずという言葉があるわけでございまして、そうしたことで交渉をやっていかなければいけませんし、ある意味、私もそうですし、ブリンケン長官やほかのG7の外務大臣の皆さんともいろいろなお話をしますけれども、同じようなお考えなんだろうというふうに思っております。
商社時代に最後の落としどころというような言葉をよく使っておりましたけれども、それをどこに見据えるのかというのは、今委員がおっしゃったような、いろいろなことに思いを巡らせて出てくるものではないかなというふうに思っております。
○吉良分科員 日本の国益を考えながらのウクライナ対応、今回、日本にとっては、これだけ寒い冬、貴重なLNGをヨーロッパに融通するというようなこともしながら、ある意味、米国との同盟を重視し、そして、同盟国の同盟国、そういう友好国とのきずなを大事にし、ある意味では連帯を示すためにLNGを差し出していったんだというふうに思います。恐らく、これは、ヨーロッパが必要としているLNGの量から比べたら、正直言って量的には意味を成さない。けれども、連帯の意を示すということでは意味があるんだろうと思っています。
サマワに自衛隊を派遣したとき、私はどう言っていたかというと、野党議員としては反対をすると。これは野党だから常に反対ということでは、当時の、一国のリーダーとしての責任がない立場であれば反対をする、ただ、自分が総理であれば、やはり派遣を決定するだろうということを言っていました。
その際に、私が自衛隊の皆さんに訓示をするのは、灼熱の地イラク・サマワで、日本海、東シナ海、南西諸島の防衛に当たってくれ、サマワで今言ったところの防衛に当たってくれということを訓示したと思っています。それだけ、今言った米国との関係、そして同盟国の同盟国との関係を重視してのLNGの供給だというふうに思っておりますし、それ自体は私は国益にもとることではないとこれは信じておりますけれども、ただ、具体的に、私は、具体的というより、なぜここまで米国も、また米国をリーダーとするNATOも、ウクライナのNATO加盟の余地を残すというか、余地は私、残していいと思っているんです、今現在入る可能性が高いということを取り下げずに、武力紛争もやむなし、この考え方が分からないんですね。私が、今度はNATOの立場であれば、未来永劫、ウクライナをNATOに入れません、こういうコミットは、これはまたできないですよね。けれども、今の緊張状態を和らげる、しかも、コロナの時期で、世界経済がずっと傷んで、そのためにいろいろなところが傷んでいる、それを考えたら、少なくとも暫定的にこの場を収めるための妥協案、私は米国なりNATO側から出してもいいと思っているんですね。
一つは、中立国というのを促すという手もないわけではないと思いますけれども、私は、今言ったように、NATO、米国に対して、さっき言った、一〇〇対ゼロではなくて、三〇か四〇は譲るという方策はないものか、それを日本政府から提案してはどうなのか。水面下ではもしかしたらやっているかもしれません。
というのも、冒頭に、二月三日の問題意識として披露しましたけれども、日本にとってみれば、北方領土の解決があり、そして、化石燃料は今、目の敵にはされていますけれども、しばらくの間は化石燃料が必要、そういう中にあって、サハリンあり、ヤマルあり、このロシアとの関係を絶対に悪化させてはいけない。かえって、これをチャンスとして、ロシアから多くのものを国益として得る、このような戦略が必要だと私は思っているんですけれども、その妥協案の提示について、又はそれを踏まえた日本の国益について、これは最後の質問になると思いますけれども、大臣の御見解を伺いたいと思います。
○林国務大臣 先ほど申し上げましたように、バイデン大統領とプーチン大統領の間で、外交的な取組を継続する用意がある旨を表明をされております。クアッドで日米外相会談を行いましたが、やはりその場においても、米国は外交努力というのは最後まで継続していくというようなこと、表明があったところでございます。
そうした中で、我々として緊密に連携を取るというところまでは、私、ここで申し上げられることができるわけですが、具体的なことは差し控えさせていただかなければならないと思っております。
その上で、先ほど、LNGのお話がありましたけれども、このLNGというのはもちろん、先ほど委員からお話ししていただいたように、欧州と連帯を示すという観点で行うわけでございますが、もう一つ、資源の上流開発投資を含めて、エネルギー安全保障確保の重要性、これを改めて想起をさせる契機になるものとも同時に考えておるわけでございますので、そういった意味でも、引き続き、G7を始めとする国際社会と連携して適切に対応していきたいと考えております。
○吉良分科員 ロシアとの決定的な亀裂を避けたいという思いと、天然ガスまた石油等をロシアに依存している、日本は依存し切っているわけではありませんけれども、そういう意味ではドイツとある意味では近い状況にあるというふうに思っておりますので、当然もうやっておられると思いますけれども、ドイツと密に連携しながら、この問題を必ず平和裏に終わらせて、ウクライナの人たちを誰一人犠牲にすることなく、国際経済に悪影響を及ぼすことのない解決策を日本政府としても積極的に発信していくということをお願いいたしまして、私の質問を終わります。
ありがとうございました。